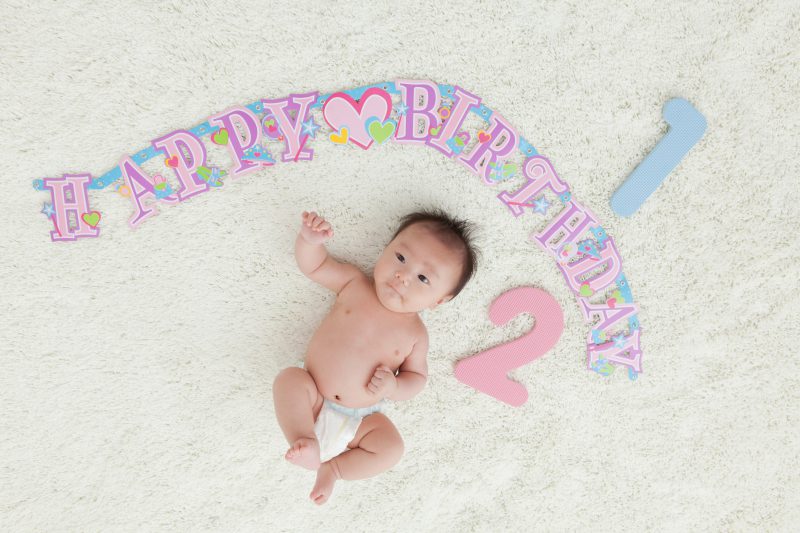【生後6ヶ月】働くママの悩みとは?
赤ちゃんが生後6ヶ月を迎えると、仕事復帰を果たすママも増えてくるのではないでしょうか。
生後6ヶ月の赤ちゃんが保育園へ行き始めると、驚くほど頻繁に風邪を引き、熱を出します。
仕事復帰してから数か月は「欠勤ばかりで思うように仕事ができなかった」というのは働くママによくある話。
しかしあまりに頻繁だと、その度に仕事を休むママは困ってしまうのが本音でしょう。
赤ちゃんの体調不良は、働くママにとって最も深刻な悩みかもしれませんね。
そこで今回は、生後6ヶ月の赤ちゃんを育てる働くママの悩み「赤ちゃんの風邪と仕事」について考えてみます。
入園後赤ちゃんの風邪が続いて仕事に行けない!と悩んでいるママは、是非チェックしてみてください。
【生後6ヶ月】赤ちゃんはなぜ風邪を引きやすいの?
今までは元気だった生後6ヶ月の赤ちゃんが、保育園へ通い始めると頻繁に熱を出すのはなぜでしょうか?
【たくさんの人や外の世界との関わり】
生後6ヶ月の赤ちゃんは入園すると、たくさんの人や外の世界との関わりができます。
それと同時にさまざまなウイルスや感染症に触れる機会が増えるのです。
さらに生後6ヶ月の赤ちゃんはよだれや鼻水、なんでも口に入れてしまうなど、菌が体内に侵入しやすい状態。
まだ自分でうがいや手洗いなどの感染対策もできないため、他の子どもとウイルスや感染症を移し合ってしまいます。
熱が下がったから保育園への登園を再開したのに、またすぐに熱が出るというのを繰り返す場合も。
【ママからの免疫が切れる時期】
生まれる時にママから貰った免疫が、生後6ヶ月以降に減少するのも関係していると言われます。
その頃から自身の免疫が発達してくる1歳過ぎまでは、免疫力が低く風邪を引きやすいようです。
この2つの理由が重なることで、より一層風邪を引きやすくなっているのかもしれませんね。
【生後6ヶ月】仕事を休みづらいときは?
生後6ヶ月の赤ちゃんが熱を出すと、仕事を休むママは多いでしょう。
しかしあまりに頻繁だと、休みづらいですよね。
働くママ達はそんな時、どのような対応をしているのでしょうか。
【パパに仕事を休んでもらう】
赤ちゃんが風邪の時はママだけでなく、パパにも協力してもらいましょう。
仕事があって休みにくいのは、パパもママも一緒です。
風邪を引いたら数日間保育園を休まなければいけません。
交代で休めばママの負担も減るはず。
共働きでの育児は、パパとママが協力することが大切ではないでしょうか。
【おじいちゃんおばあちゃんにお願いする】
どちらかの実家が近ければ、看病をお願いする場合も。
パパとママは仕事を休まなくても良いため、とても助かりますよね。
しかし赤ちゃんの体調不良時はお世話が大変だったり、看病をしていて風邪が移ったりすることもあります。
あまり負担にならない程度に、お願いしたいですね。
【病児保育を利用する】
風邪を引いた赤ちゃんを保育士や看護師が預かってくれる病児保育は、働くママの強い味方です。
家族以外で、風邪の時でも赤ちゃんを預けられる場所があると心強いですよね。
そのため通える範囲の全ての病児保育に登録している、というママも。
・利用手順がめんどう
・予約が取りづらい
・お金がかかる
などのデメリットもありますが、ママにとってはとても助かるサポートです。
事前に近くの病児保育を調べておき、登録をしておくと役に立つかもしれませんよ。
【テレワークへの切り替えを相談する】
赤ちゃんが熱を出して保育園に行けないとき、在宅で仕事ができれば休まなくて済みます。
生後6ヶ月の赤ちゃんの看病をしながらのテレワークは大変ですが、欠勤しなくて良いとママも助かりますよね。
体調不良が重なって休みづらいときは、上司に相談してみると良いでしょう。
【生後6ヶ月】働くママの風邪対策
生後6ヶ月の赤ちゃんを育てながら働く場合、体調不良を視野に入れた対策はとても重要です。
働くママができる対策を、いくつかご紹介します。
【予防接種を受けておく】
感染症対策として、予防接種はしっかりと受けておきましょう。
ある程度の感染を防ぐだけでなく、発症しても重症化を抑えられます。
【ママの体調管理】
赤ちゃんの風邪は、身近なママに感染しやすいようです。
頻繁に風邪をもらっていると、自分の体調不良でなかなか休めないママはつらいですよね。
赤ちゃんだけでなく、ママの体調管理にも気をつけましょう。
【休んでも迷惑がかからないようにしておく】
普段から資料は分かりやすくまとめておいたり、重要な情報は誰かと共有しておいたりといった、仕事での工夫も必要です。
急に休んでもできるだけ迷惑がかからないようにしておけば、ママも同僚も慌てずに済みますよね。
頻繁に休む可能性があっても、きちんと対策をしておけば、周りの反応もママの気持ちも違うのではないでしょうか。
まとめ
赤ちゃんの体調不良が続くと仕事も休みがちになり、働くママにとっては悩みのタネですよね。
赤ちゃんは風邪を引くことで免疫を獲得し、強くなっていきます。
個人差はありますが入園して半年から一年を過ぎると、少しずつ風邪も落ち着いてくるようです。
1歳過ぎて赤ちゃん自身の免疫が発達すれば、元気に登園できる日も増えるかもしれません。
それまで周りと協力しながら、なんとか乗り越えていきたいですね。